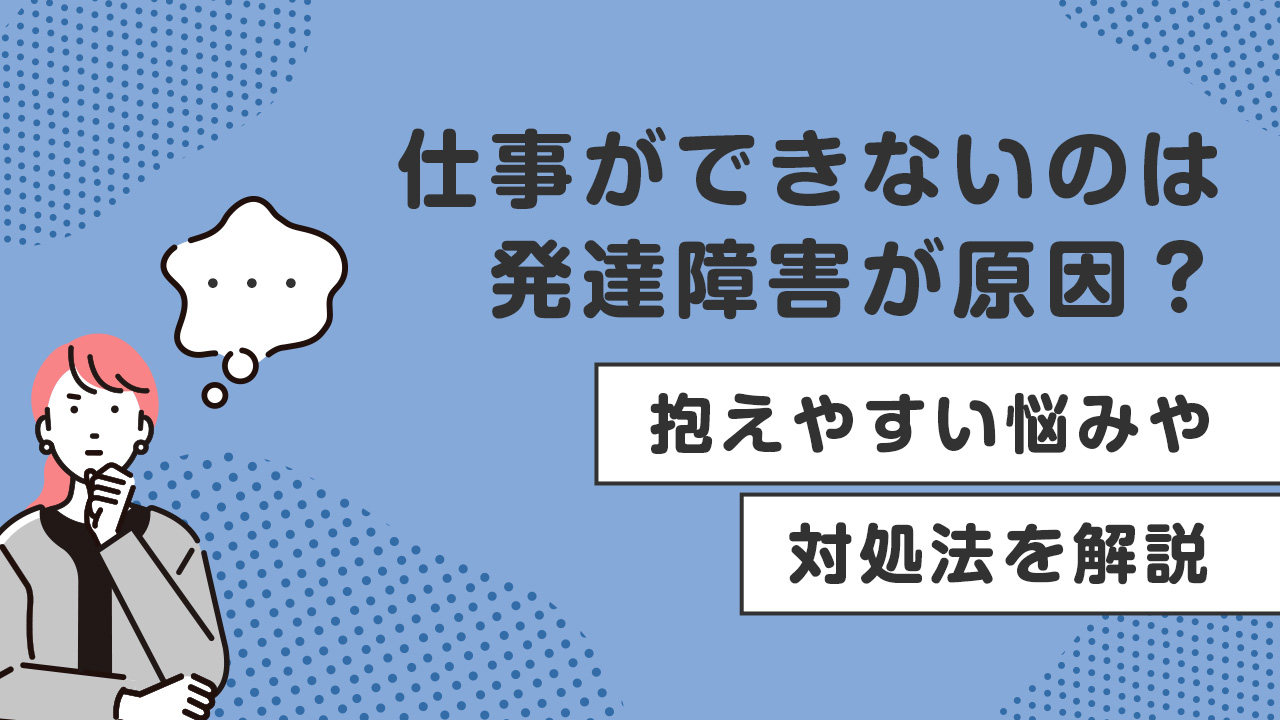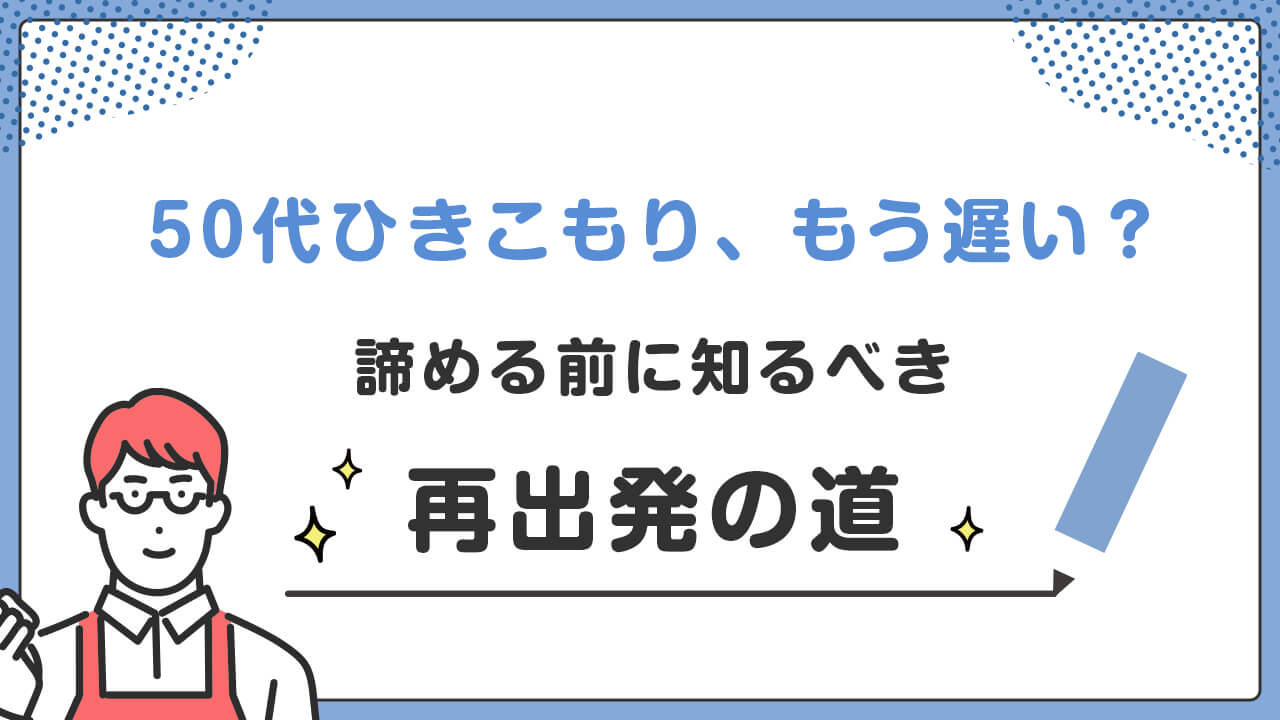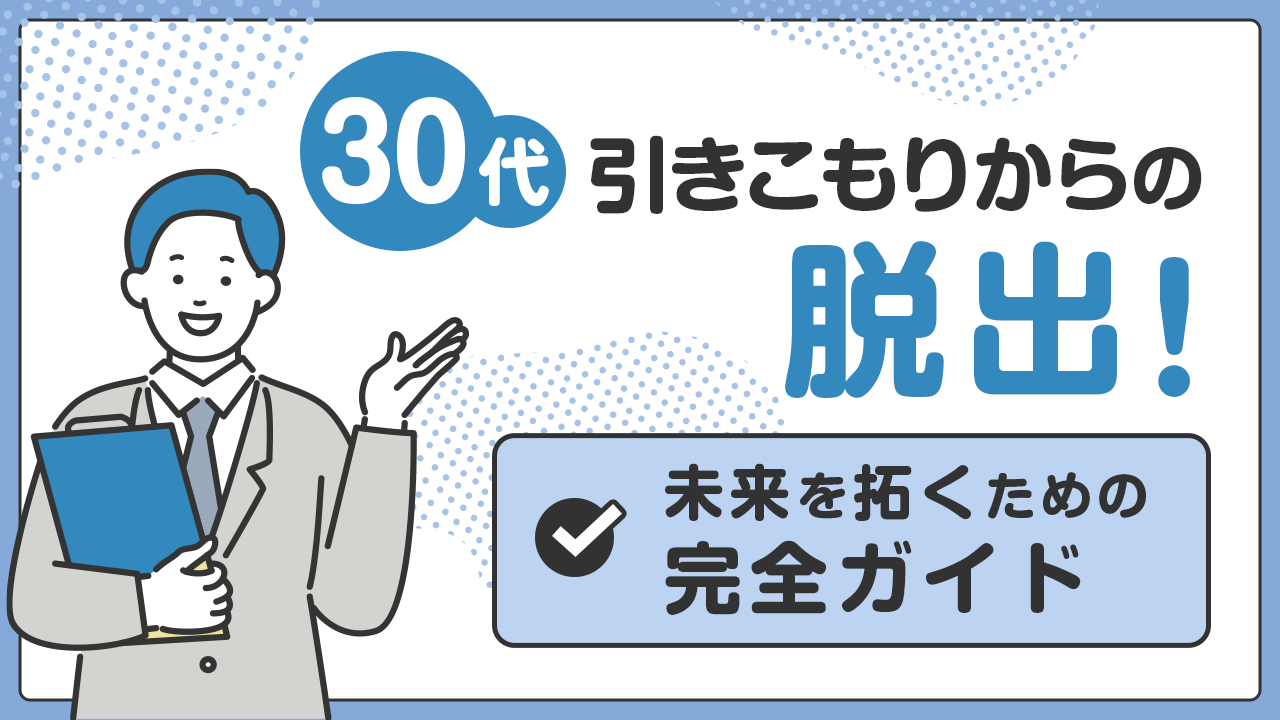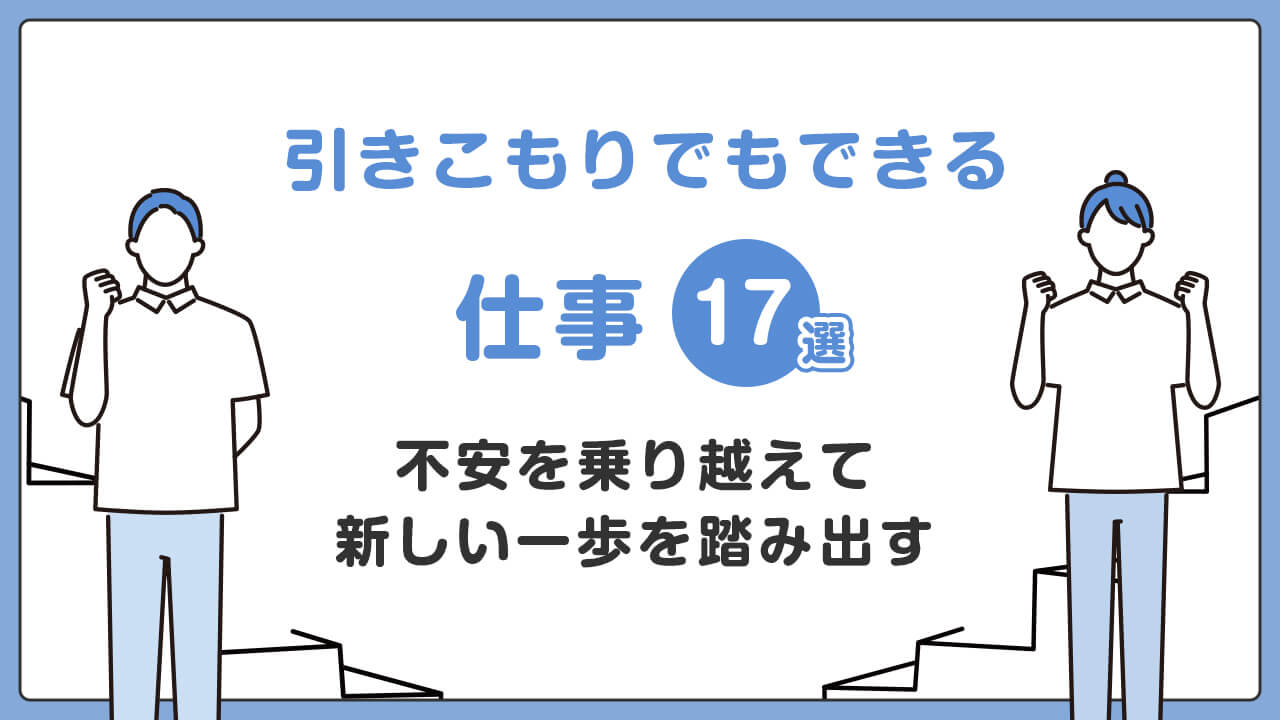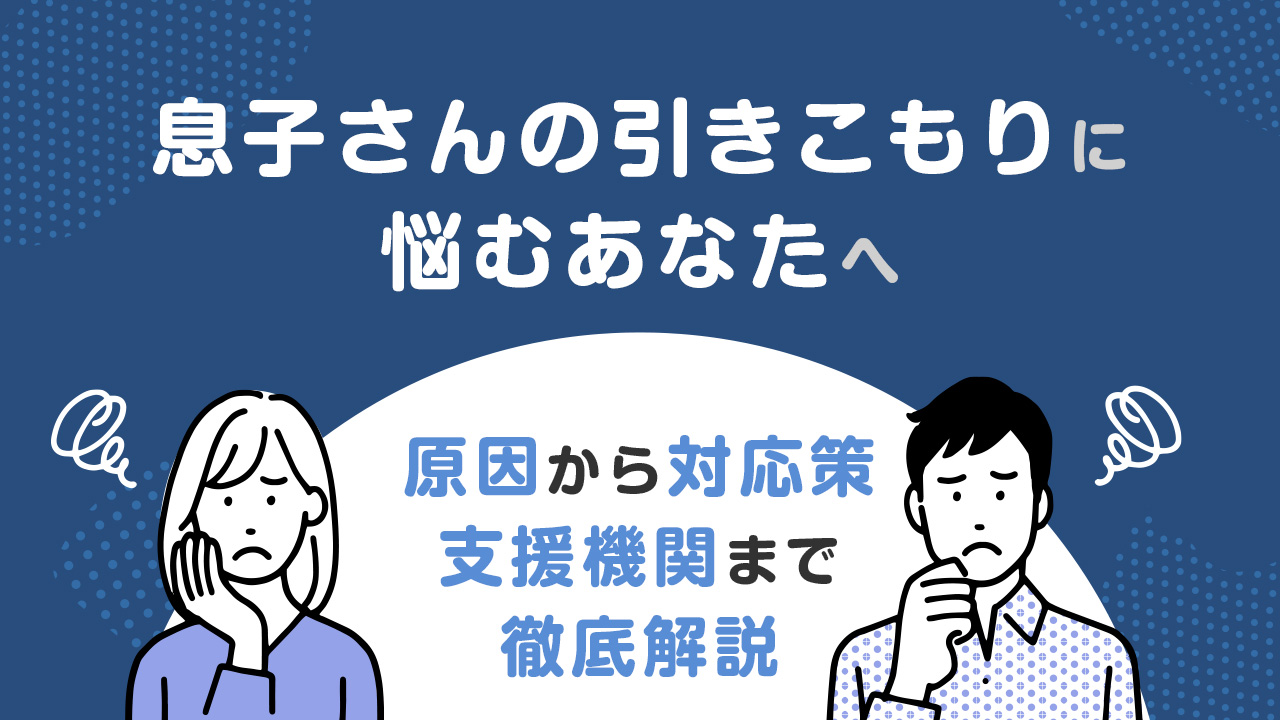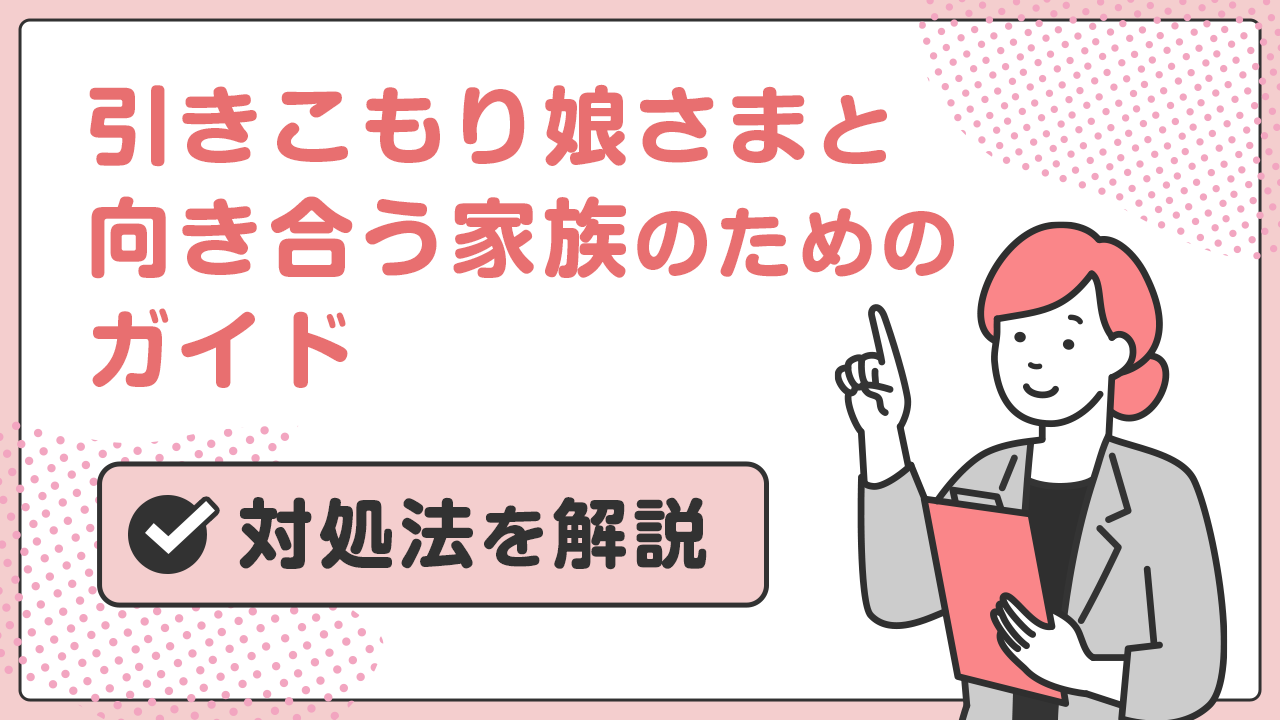
「娘が引きこもりで悩んでいる」という悩みを抱えていませんか?
大切な娘さまが、なかなかお部屋から出てこられず、外の世界との関わりを避けるようになってしまうと、「この先、どうなってしまうのだろう」「社会に戻れる日が来るのだろうか」と、親御さまとしては心配が尽きないことと思います。
娘さまが引きこもられている時、その心は大変デリケートで、傷つきやすい状態にあります。そのため、ご家族の些細な言動が、良かれと思ってのことであっても、かえってお嬢様の心を閉ざし、事態を長引かせてしまうことも少なくありません。
この記事では、札幌市西区で就労継続支援B型事業所を運営する「ジャバメート」が、社会と繋がるための一歩を踏み出すための具体的な方法について、丁寧に解説いたします。
娘さまの引きこもりが長期化しやすい親御さまの対応パターンや、社会復帰に向けてご家族が心がけるべきことについても触れていますので、娘さまのことで深く悩んでいらっしゃる親御さまにとって、少しでもお役に立てれば幸いです。
札幌市西区にある就労継続支援B型事業所「ジャバメート」では、ひきこもりで外出が難しかった方が「社会復帰できた!」という嬉しいお声をたくさんいただいています。お電話またはお問い合わせフォームから「お申込み」いただき、見学・体験ができます。ぜひお気軽にご相談にいらしてください。
目次
なぜ娘は引きこもってしまうのか?

大切な娘さまがなぜ引きこもってしまうのか、その理由が分からず、親御さまご自身を責めてしまうこともあるかもしれません。しかし、引きこもりは決して本人の怠慢やわがままだけが原因ではありません。様々な要因が重なっている場合が多いです。
今回は娘さまが引きこもってしまう理由を5つ解説します。
- 社会への不安、自信の喪失
- 過去の経験やトラウマの影響
- 親との関係性
- 発達障害や精神疾患の可能性
- 本人なりの理由と葛藤
社会への不安、自信の喪失
社会に出ることへの漠然とした不安感、人間関係の難しさ、あるいは仕事や学業でのつまずき経験から自信を失い、一歩を踏み出す
いじめ、不登校、受験や就職活動の失敗、失恋、職場のハラスメントなど、過去の辛い経験が心の傷となり、トラウマとして残っていることも考えられます。その経験がフラッシュバックし、再び傷つくことを恐れて、人との関わりや社会から距離を置くことで自分を守ろうとしているのかもしれません。
親御さまとの関係性
決してそう望んだわけではなくとも、親子関係が引きこもりの一因となることもあります。過度な期待や干渉、逆に無関心であったり、親御さん自身が抱える不安がお嬢様に影響を与えている可能性も否定できません。娘さまなりのSOSを、うまく表現できずにいるのかもしれません。
発達障害や精神疾患の可能性
発達障害(ASD、ADHDなど)の特性により、コミュニケーションや環境への適応が難しく、生きづらさを感じているケースや、うつ病、不安障害、統合失調症といった精神疾患が背景に隠れている場合もあります。これらの場合、医療機関や専門家のサポートが不可欠です。
本人なりの理由と葛藤
引きこもっている娘さま自身も、決して楽なわけではありません。「このままではいけない」「何とかしたい」という気持ちと、「どうすれば良いか分からない」「怖い」という気持ちの間で、日々葛藤しています。引きこもることで、一時的に心の安定を保とうとしている場合も考えられます。
引きこもりの長期化がもたらす悪循環
引きこもりが長期化すると、生活リズムの乱れ、体力や気力の低下、社会との隔絶による孤独感の深化、自己肯定感のさらなる低下といった悪循環に陥りがちです。ご家族も疲弊し、家庭内の雰囲気が悪化することで、娘さまはさらに孤立を深めてしまうこともあります。
まずは理解することから
お嬢様の引きこもりの背景には、様々な要因が複雑に絡み合っていることを理解することが、最初の大きな一歩です。原因を一つに特定しようとしたり、誰かの責任にしたりするのではなく、娘さまが置かれている状況や心情に、まずは寄り添う姿勢が大切です。
今、娘さまのために親ができること
娘さまが引きこもっている時、親として何ができるのか、悩むことも多いかと思います。しかし、親御さまの存在は、娘さまにとって最後の砦であり、安心できる存在でもあります。焦らず、娘さまのペースを尊重しながら、少しずつ繋がりを取り戻していくための関わり方を見ていきましょう。
今回は6つ紹介します。
- 頭ごなしの否定や説教はNG
- 小さな変化を見逃さない
- 会話のきっかけを作る
- 家庭内の居心地を良くする
- 専門機関への相談を検討する
- 同じ悩みを抱える家族との交流
頭ごなしの否定や説教はNG
「いつまでそうしているの?」「将来どうするつもり?」といった言葉は、娘さまを追い詰めるだけで逆効果です。娘さまの今の状態や気持ちを頭ごなしに否定したり、正論で説教したりするのは避けましょう。
小さな変化を見逃さない
「おはようと返事をしてくれた」「部屋から少しだけ顔を出した」「食事を一緒に取った」など、些細なことでも構いません。娘さまの小さな変化を見逃さず、心の中で喜び、そして可能であれば「一緒にご飯を食べられて良かった」などと、さりげなく肯定的な言葉で伝えてみましょう。
会話のきっかけを作る
無理に引きこもりの話題に触れる必要はありません。娘さまが好きだったもの、興味がありそうなこと(テレビ番組、ペットのことなど)を、話しかけてみるのも良いでしょう。返事がなくても、親御さまが気にかけているというメッセージは伝わります。
家庭内の居心地を良くする
娘さまにとって、家が唯一安心できる場所である必要があります。家庭内が常に緊張していたり、言い争いが絶えなかったりすると、娘さまはますます心を閉ざしてしまいます。親御さま自身がリラックスし、穏やかな家庭環境を作ることを意識しましょう。
専門機関への相談を検討する
ご家族だけで抱え込まず、専門家の力を借りることも非常に重要です。引きこもり支援センターや精神保健福祉センター、そして私たち「ジャバメート」のような就労継続支援B型事業所も、ご本人だけでなくご家族からの相談も受け付けています。客観的なアドバイスや具体的なサポートを受けることで、解決の糸口が見えてくることがあります。
同じ悩みを抱える家族との交流
「こんな悩みを抱えているのは自分だけではないか」という孤立感は、親御さまにとっても辛いものです。引きこもりの家族会や親の会などに参加し、同じ経験を持つ方々と気持ちを分かち合い、情報を交換することで、心の負担が軽減されることがあります。
親自身の心のケアも大切に
娘さまのことを心配するあまり、親御さまご自身の心身が疲弊してしまっては元も子もありません。親御さまが笑顔でいることが、娘さまにとっての安心感に繋がります。自分のための時間を作り、趣味を楽しんだり、友人と話したりして、意識的に休息を取り、心の健康を保つことも忘れないようにしましょう。
娘さまが一歩踏み出すために
娘さまが自ら一歩を踏み出すためには、安心感と自己肯定感を取り戻すことが不可欠です。親御さまは、娘さまの小さな挑戦を温かく見守り、サポートする姿勢が大切になります。
今回は、娘さまが一歩踏み出すための方法を7つ紹介します。
- 小さな目標設定から始め、成功体験を積み重ねる
- 興味のあること、得意なことを見つける
- 焦らず、自分のペース!
- 過去の成功体験を思い出す
- 周囲のサポートを素直に受け入れる勇気
- 未来への希望を描く
- まずは「話す」ことから
小さな目標設定から始め、成功体験を積み重ねる
「決まった時間に起きる」「簡単な家事を手伝う」など、娘さまにとって負担の少ない小さな目標を設定し、それをクリアすることで達成感を味わえるようにサポートしましょう。目標を達成すること自体よりも、その過程での努力や挑戦する気持ちを褒めることが大切です。
興味のあること、得意なことを見つける
娘さまが以前好きだったこと、少しでも興味を示せるもの、得意なことなどを一緒に探してみましょう。読書、音楽、映画鑑賞、絵を描くこと、料理、ゲームなど、どんなことでも構いません。好きなことに没頭する時間は、心のエネルギーを充電し、自己肯定感を高めるきっかけになります。
焦らず、自分のペース!
社会復帰を急かしたり、周囲と比較したりすることは禁物です。「早く何とかしなければ」という焦りは、娘さまにも伝わり、プレッシャーを与えてしまいます。娘さまには娘さまのペースがあります。ゆっくりでも、一歩ずつ進んでいくことを見守りましょう。
過去の成功体験を思い出す
過去に何かを成し遂げた経験や、褒められた経験などを思い出させ、自信を取り戻す手助けをすることも有効です。「あの時も頑張れたのだから、きっと大丈夫」という気持ちが、次の一歩を踏み出す勇気に繋がります。
周囲のサポートを素直に受け入れる勇気
専門機関や支援者からのサポートを素直に受け入れることも大切です。娘さま自身が「助けてほしい」と言えるようになるには時間がかかるかもしれませんが、親御さまが先に相談機関と繋がり、道筋をつけておくことも一つの方法です。
未来への希望を描く
すぐに具体的な将来像を描けなくても構いません。「こんなことができたらいいな」「あんな場所に行ってみたいな」といった、ささやかな希望や夢について、親子で語り合える時間を持てると良いでしょう。未来に少しでも明るいイメージを持つことが、生きる力になります。
まずは「話す」ことから
自分の気持ちや考えを安心して話せる相手がいることは、非常に重要です。無理に聞き出そうとせず、娘さまが話し始めたら、じっくりと耳を傾け、共感する姿勢を示しましょう。言葉にできない想いも、受け止めることが大切です。
家族以外のサポート|専門機関や地域の力を借りる
引きこもりからの回復には、親御さまの努力だけでは限界がある場合も少なくありません。専門機関や地域の様々なサポートを積極的に活用しましょう。
専門機関のサポートを活用する方法として7つ紹介します。
- 地域のひきこもり相談支援センター
- 精神保健福祉センター
- 若者サポートステーション(サポステ)
- 医療機関(精神科・心療内科)
- NPO法人・支援団体:多様なサポートプログラム
- 家族会・当事者会
- オンラインでの相談窓口
地域のひきこもり相談支援センター
各都道府県や市町村に設置されており、専門の相談員が対応してくれます。ご本人だけでなく、ご家族からの相談も可能です。情報提供や関係機関への紹介などを行っています。
精神保健福祉センター
心の健康に関する相談や支援を行う専門機関です。精神科医や臨床心理士などの専門家が在籍しており、必要に応じて医療機関への紹介も行っています。
若者サポートステーション(サポステ)
働くことに悩みを抱える若者とその家族を対象に、就労に向けた相談や支援プログラムを提供しています。コミュニケーション訓練や職場体験なども行っています。
医療機関(精神科・心療内科)
引きこもりの背景に精神疾患が疑われる場合や、不眠、不安、抑うつなどの症状が強い場合は、精神科や心療内科の受診を検討しましょう。適切な診断と治療を受けることで、症状が改善し、回復への道が開けることがあります。
NPO法人・支援団体:多様なサポートプログラム
引きこもり支援を専門に行うNPO法人や民間団体も多数存在します。居場所の提供、訪問支援、共同生活プログラム、就労訓練など、多様なサポートを行っています。娘さまの状況やニーズに合った団体を探してみましょう。
家族会・当事者会
同じ悩みを持つ家族や当事者が集まり、体験を語り合ったり、情報を交換したりする場です。孤独感を和らげ、支え合うことができます。
オンラインでの相談窓口
直接出向くことに抵抗がある場合は、電話やメール、チャットなどで相談できるオンライン窓口も活用できます。匿名で相談できるところも多く、気軽に利用しやすいのが特徴です。
社会との繋がりを少しずつ|焦らず、段階的に
引きこもりから社会復帰を目指す道のりは、一足飛びにはいきません。小さなステップを積み重ね、焦らず段階的に進めていくことが大切です。
小さなステップとして7つ紹介します。
- まずは家の中でできること:役割を持つ、家事に参加する
- オンラインでの交流:趣味のコミュニティ、SNS
- 短時間・短期間のアルバイト:社会との接点を作る
- ボランティア活動への参加:他者との関わりを持つ
- 地域のイベントや講座に参加する:新たな興味を発見
- 就労支援プログラムの活用:社会復帰への準備
- 失敗を恐れない:小さな一歩を応援する
まずは家の中でできること:役割を持つ、家事に参加する
「洗濯物を畳む」「食事の準備を手伝う」「ペットの世話をする」など、家の中でできる簡単な役割をお願いしてみましょう。誰かの役に立っているという実感は、自己肯定感を高めます。
オンラインでの交流:趣味のコミュニティ、SNS
対面でのコミュニケーションが難しい場合は、オンラインでの交流から始めてみるのも良いでしょう。共通の趣味を持つ人々のコミュニティに参加したり、匿名性の高いSNSで自分の気持ちを発信したりすることで、社会との繋がりを感じられることがあります。
短時間・短期間のアルバイト:社会との接点を作る
体力や気力が少し回復してきたら、週に数日、1日数時間程度の短時間・短期間のアルバイトから始めてみるのも一つの方法です。無理のない範囲で社会との接点を持つことで、働くことへの自信を取り戻すきっかけになります。
ボランティア活動への参加:他者との関わりを持つ
地域のごみ拾いやイベントの手伝いなど、短時間で参加できるボランティア活動も、社会貢献を実感しやすく、他者との自然な関わりの中でコミュニケーション能力を養う良い機会となります。
地域のイベントや講座に参加する:新たな興味を発見
地域の広報誌や公民館のお知らせなどをチェックし、お嬢様が興味を持てそうなイベントや講座に参加を促してみましょう。新たな興味や関心事が見つかるかもしれません。
就労支援プログラムの活用:社会復帰への準備
就労継続支援B型事業所である「ジャバメート」のような場所では、個別の支援計画に基づき、軽作業や創作活動、コミュニケーション訓練などを通じて、社会復帰への準備を無理なく進めることができます。同じような仲間と出会えることも、大きな支えになります。
失敗を恐れない:小さな一歩を応援する
社会との繋がりを取り戻す過程で、うまくいかないことや失敗もあるかもしれません。しかし、それを責めたりせず、「また次があるよ」「よく頑張ったね」と、お嬢様の小さな一歩を温かく応援し続けることが大切です。
よくある疑問と不安|専門家が答えます
親御さまが多く抱える疑問や不安を5つ紹介します。
- いつまでこの状態が続くのでしょうか?
- 無理やり外に出すべきでしょうか?
- 動画やゲームばかりで心配です。
- 親として何が一番大切ですか?
- 娘の将来が不安で仕方ありません。
それぞれ解説しているのでぜひ参考にしてみてくださいね。
Q:いつまでこの状態が続くのでしょうか?
残念ながら、「いつまで」という明確な期間を申し上げることはできません。引きこもりの期間や回復のペースは、ご本人の状態や環境、サポートの状況によって大きく異なります。大切なのは、焦らず、お嬢様のペースを尊重し、長期的な視点で見守ることです。専門機関と連携しながら、一歩ずつ進んでいくことが重要です。
Q:無理やり外に出すべきでしょうか?
無理やり外に連れ出すことは、多くの場合逆効果です。娘さまの恐怖心や不信感を強め、さらに心を閉ざしてしまう可能性があります。まずは安心できる家庭環境を整え、自ら動き出すエネルギーを蓄えられるようにサポートすることが大切です。
Q:動画やゲームばかりで心配です。
動画やゲームが、娘さまにとって唯一の気晴らしや社会との繋がりになっている場合もあります。頭ごなしに禁止するのではなく、まずはその行動の背景にある気持ちを理解しようと努めましょう。少しずつ他のことにも興味を持てるように、さりげなく声をかけたり、他の活動を提案したりすることも有効ですが、無理強いは禁物です。
Q:親として何が一番大切ですか?
娘さまを信じ、無条件の愛情を伝え続けることです。そして、娘さまのありのままを受け入れ、安全基地としての役割を果たすこと。また、親御さま自身が一人で抱え込まず、専門家や支援者と繋がり、心身の健康を保つことも同様に大切です。
Q:娘の将来が不安で仕方ありません。
娘さまの将来を案じるお気持ちは、親として当然のことです。しかし、その不安が娘さまに過度なプレッシャーとして伝わらないように注意が必要です。今は、将来のことよりも、「今」の娘さまの心に寄り添い、安心感を与えることを最優先に考えましょう。専門機関のサポートを受けながら、少しずつ未来への希望を見つけていくことが大切です。
おわりに
30代の娘さまの引きこもりという、出口の見えないトンネルの中にいるように感じ、お母様ご自身も心身ともに疲れ果てていらっしゃるかもしれません。しかし、決して一人ではありません。
この記事でお伝えしたように、娘さまの心の内を理解しようと努め、焦らず、娘さまのペースに合わせた関わり方を続けることが、未来への扉を開く鍵となります。そして、ご家族だけで抱え込まず、私たち「ジャバメート」のような専門機関や地域のサポートを積極的に活用してください。
娘さまの引きこもりで悩んでいる方は、この記事でご紹介した内容を参考にしてみてください。
まずはジャバメートでお仕事に挑戦してみよう!

ジャバメートは、札幌市西区二十四軒(札幌中央卸売市場向かい)にある、就労継続支援B型事業所です。地下鉄東西線「二十四軒駅」から徒歩8分と、地下鉄で通える便利なアクセス。
ジャバメートの5つの特徴
- 高収入を目指せる! 頑張り次第で、高い工賃をGET!
- 洗濯スキルがUP! 自分の洗濯物を週1回、仕事として洗えます。
- 自分に合った仕事を選べる! 洗濯、ポスティング、清掃、チラシ折りなど、色々な仕事があります。
- 楽しいイベント盛りだくさん! レクリエーションで、仲間と楽しい時間を過ごせます。
- アットホームな雰囲気!
「働きたいけど、続けられるか不安…」
「体力やメンタル面に自信がない…」
そんな方も、ご安心ください。ジャバメートは、一人ひとりのペースに合わせて、丁寧にサポートします。
普段のジャバメートの様子はInstagramで!
見学はいつでもOK! ご予約いただければ、職員がご案内します。
ご同行も大歓迎です! ご家族や支援者の方と一緒に来ていただけます。
- 交通費として1,000円支給!
- 体験ご希望の方は、昼食をご提供!
お気軽にお問い合わせください。
電話での予約はこちら
見学・体験の申込はこちら!
 札幌 就労継続支援B型事務所
札幌 就労継続支援B型事務所